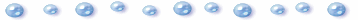|
前夜 鬱陶しいほど降り続く雨に、若島津は溜息を吐く。 ワイパーがフル回転しているが、見通しの悪さは増すばかりだ。もとより慎重な運転をしているが、こういう日は特に気をつけないと、なにがあるかわからない。この時期に交通事故でも起こしたら、それこそすべてが水の泡だ。 ここ最近の緊張感に包まれた生活とも明日でお別れだ。 通過点のひとつに過ぎないとわかっていても、明日選ばれなければ、結局はそれで終わりだ。 特に、四年後には30代になる自分には、次はないものと覚悟していた方がいいだろう。四年後も今の実力を落とさずに世界の選手と渡り合う自信はあるが、外国人の代表監督というものは、どういうわけか若い選手が好きな人間が多いらしい。自分もそのおかげで選ばれたことがありながら、そんなことを思う。 とにかく今は二十三人の中に選ばれることが第一だ。 明日は、ワールドカップの代表選手が発表されるのだった。
「っちぇーっ!」 「どうしてあそこで点が取れねえんだよ!」 「俺だったら!」 衛星中継された試合を、寮の食堂で皆で見た。深夜だったが、そんなことは関係なく皆で夢中になって応援して声を上げた。 だが、結局日本は勝つことが出来なかった。 口々にあーだこーだと試合の分析やらグチやらを言いながら、しばらくは誰も部屋に帰らなかったが、いつまでも起きているわけにもいかない。誰からともなく、それぞれの部屋へと戻り始めた。その中で、日向だけが屋上へと向かった。 眠る気になれなかったから、若島津はその背中をポンと叩いて、無言でついていくという意思表示をした。日向は勝手にしろと目で答えた。 日向とは小学生の時からの付き合いで、ずっと一緒にサッカーをやってきた。 私立の中学・高校に来てまで一緒にサッカーをする仲だったが、普段の生活ではいつも一緒にいるという訳ではない。むしろ、つるむ友人はそれぞれに違った。 口数が少なく、ぶっきらぼうな態度が多い日向とは何かにつけてよくケンカもしたが、決して彼のことは嫌いではない。 「あちこちで灯りが付いてるな。みんな、試合を見ていたのかな」 「さあな」 屋上の柵に身を任せながら周囲を見渡す。田舎の学校だから、見えるものといったら学校関係の施設と民家、それに山と木々ばかりだ。が、いつもは暗く静かな風景も、さすがに今日ばかりはあちこちから光が漏れている。 そんな風景を見つめていたら、気持ちいい夜風が吹いてきた。 「おまえがあの場にいたら、点を取れたかもな」 話を振ると、日向は「無理だろ」と呆気なく返した。 ユース代表にも選ばれ、高校生にして日本代表か!?と噂されるほどの日向とは思えない言葉だ。 「自信がない?」 「このままの俺じゃあダメだ。日本の中で渡り合えても世界じゃまだ甘い。俺はあの連中のように負けたりしない」 そう口にした日向の目は夜空に向けられながらも、更にその先の何かを見ているようだった。 「……世界に出るつもりか?」 「ああ。いつまでも井の中の蛙でいたくねえよ」 若島津は頷くだけで、それ以上の言葉は言えなかった。 日向は今、自分の道を定めたのだと思った。恐らく高校在学中に動き出すに違いない。今までも彼へのプロチームからの誘いはいくらでもあった。今時、高校生Jリーガーも珍しくない。 だが日向はきっとそれを飛び越えて、一気に世界への道を目指すだろう。 まだガキの頃だったか、本当は学校などに行かず、すぐにでもサッカーが出来る環境で生きたいのだと言っていたことがある。ライバルの翼がブラジルに飛び立った時も、悔しさに唇を噛んでいたのも知っている。だからきっと、今度こそ彼は大きく飛び立つに違いない。 日向が羨ましいと思う。 サッカーで生きていこうという気持ちは自分もあるが、そこまで思い切れていない。それどころか、いまだに空手家の父親と後継ぎのことで揉めている状態で、サッカー一筋に生きていく状況さえ作れていない。 負けたくないなあと思う。 何にかはわからないが、とにかく負けたくない。 空を見上げると、鏡のように輝く半月と数え切れないほどの星々が飛び込んでくる。 煌く星の一つに自分もなれるだろうか。 いや、なるんだ。 日向とは違う道を行くことになるだろうが、行き着いた場所できっとまた戦うんだ。 「若島津」 「ん?」 見れば、日向はヤケに真剣な目で若島津を見ていた。 「おまえも世界に出ろよ」 「日向」 「俺が点を取るだけじゃあ勝てないからな」 思わず笑みが浮かぶ。 「ああ、任せとけ」 パンッと肩を叩いて請け負った。 自信などまだ欠片しかない。 だが、今まで眠っていた何かが胸のうちで動き出すのを感じた。
運命とは皮肉なものだと、この時ほど思ったことはない。 高校卒業後にプロ入りした若島津は、当時の代表監督が若手を優先的に起用する監督だったこともあり、どうにか代表枠に滑り込んだ。 若島津よりも代表への意欲を燃やしていた日向だが、彼は選ばれなかった。 彼は高校在学中にイタリアの某チームのプリマヴェーラにチャレンジし、学生生活の後半のほとんどをイタリアで過ごし、そのままプロデビューを果たした。ちなみにイタリア行きが決まるまでには、学校関係者との間に煩雑なやり取りがいろいろあったようだが、日向はそのグチをこぼすことなく自分の意志を貫き、最後には学校側も全面協力をする形になり、高校卒業資格もギリギリで得た。日向がイタリアでレギュラーに定着するまでに1シーズンを必要としたが、着実に力をつけ、日本代表になくてはならない存在になっていった。だから、W杯メンバーは確定だった。 しかし代表発表直前に行われた国際Aマッチで右足を骨折し、日向のW杯は夢に終わった。 骨折自体はちゃんと安静にして治せば後遺症も残るものではなかったが、どう足掻いてもW杯本番には間に合わなかったのだ。 「ま、こんなもんだ」 代表メンバーの発表があった翌日、日向が若島津を尋ねてきた。 朝からのシトシト雨の中の意外な訪問者に、若島津は驚きを隠さなかった。日向との付き合いは長いが、個人的に行き来をしたことはない。それが、ギプスをしながらやってくるなんて。 「こんなにはっきり折れてるんじゃ、選びようがないもんな」 苦笑いしながらの言葉に、若島津はただ黙って酒を注ぐしか出来なかった。下手な言葉など、かえって日向には邪魔なだけだとわかっていた。自分が同じ立場なら、余計な同情などされたくない。 むしろ、こうして会いに来てくれることの方が不思議だった。悔しいはずなのに。 「そりゃあ悔しいさ。だが、ワールドカップの話題から避けて通れないからな。それにおまえが出る以上、発破はかけないとな」 「出られると決まったわけじゃないだろ。レギュラーは川田先輩なんだから」 「バカ。弱気になってんじゃねえよ」 「バカとは何だよ、バカとは」 酒が入っていたこともあり、いつになく饒舌な日向だった。もしかしたら、高校時代だってこんなに話したことはないかもしれないというくらい話をした。イタリアでの暮らしや選手間のこと、世界の選手のこと、今の代表のことなどなど、普段は表に出さない本音の部分で話し合った。 「雨が止まねえな」 一向に降り止まなさそうな雨が窓を叩き続けている。 厚いガラス戸で隔てられているからわからないが、この窓の外は雨の匂いに満ちているのだろう。 「でも、止まない雨はないぞ、日向」 「……そうだな」 そしてまた杯を交わす。 雨が止むまでと言いながら結局夜半まで飲み続け、そのまま居間で雑魚寝をしたのは、いい思い出の一つとなった。
あの日の雨よりもずっとずっと激しい雨が続いている。 あの四年後、日向は見事に代表メンバーに選ばれ、これまでの鬱憤を晴らすかのように活躍をした。 だが、八年前のあの悔しさがその原動力の一つであったに違いないと若島津は思う。 日向との関係は相変わらずだ。特に深く付き合うこともない。 例外は、なぜかW杯の代表メンバー選出の時期だけだ。 八年前に引き続き、四年前のメンバー発表後も日向は若島津のマンションに来た。実に四年ぶりの訪問だった。 「来てもいいが、四年ごとってのはどうなんだ?」 笑いながら迎え入れ、お互いに選ばれたことに対して祝杯をあげた。 「四年前は禁酒を言い渡されていたのにガブ飲みしちまって、医者にえっらい怒られたが、今回はそういうこともないしな」 「なんだよ。傷に響くからダメだって言ったのに飲ませろといったのはおまえだろうが」 そんな他愛無い話をしながら、世界のサッカーについて語った。 大会へのプレッシャーを感じつつも、今度こそベストの状態で世界に挑めることが嬉しかった。若島津はその四年前にも出場していたが、試合に出場することなく終わったから、気持ちは初めてのようなものだった。 日向とサッカーについて語っていると、いかに自分がサッカーを好きなのか、勝ちたいと渇望しているのか気付かされる。 彼の存在は、自分にとって起爆剤なのかもしれない。 そして、あれからまた四年が経った。 心ひそかに、日向がまた若島津のマンションに来ることを楽しみにしている。 約束などしていないが、明日は待っていようと思う。日向好みの美味しい酒も、この車の後部座席に丁重に積んでいる。 これもワールドカップを迎える楽しみの一つかもしれない。 なんとなくだが、予感がする。 四年後も八年後も、現役を止めた後も四年ごとにこうして会うんじゃないかと。 少し妙だけれど、こういう友情の交換もいいかもしれない。 例えば、二人して代表から外れても、戦力分析を肴に飲み明かすだろう。若手への多少のグチを混ぜながら。 そんな姿を想像するだけで、なんとなく楽しくなる。 雨足が少しだけ緩んだ気がする。 この先の信号を渡れば、マンションはすぐだ。 と、若島津はブレーキを踏んだ。急ブレーキにならないように気を付けながら端に寄って停まると、窓を開ける。 「おい!」 雨に濡れるのも構わずに身を乗り出して叫んだ。 雨の音にもかかわらず、振り返ってくれた。途端に相手の顔が明るくなる。 「どうしたんだ、一体」 「どうしたはこっちのセリフだ。なんで、この雨の中を歩いてるんだ」 「や、おまえのうちに行こうと思って」 黒い傘を差しているとはいえ、横なぐりの雨も降っていたから全身がすっかり濡れている。が、日向はそんなことも気にならないかのようだ。 この大事な時期に風邪でも引いたらどうするんだと思うが、日向らしいという気持ちの方が強くて、つい笑ってしまった。 「乗れよ」 「サンキュー」 濡れた前髪の間から覗くどこか人懐っこい目は、こうして四年ごとに会うようになってから見るようになったものだ。それまでもかなりの時間を一緒に過ごしていたが、一体どこに彼はこの目を隠していたのだろう。後部座席に落ち着いた日向を、バックミラーで覗く。 「一日早いぞ。発表は明日だろうが」 濡れ男がタオルで水分を吸い取らせているのを確認して、再び車を発進させる。マンションはもう目の前だ。 「やっぱり前夜ってのは落ちつかねえから、飲もうと思ってな。おまえもだろ」 「そうだけどさ。でも、今夜は控えろよ。二日酔いでインタビューを受けるのは真っ平ごめんだ」 「わかってるって。それより」 「なんだ?」 「傘をさしていたのに、よく俺だってわかったな」 「そりゃあ…」 思わず笑みが浮かぶ。わからないはずがない。だって。 「俺を誰だと思ってる? おまえの後ろを何年守っていると思ってるんだ」 バックミラー越しでも、日向がニヤリとしたのが見えた。 「ホント、頼もしいキーパー様だよ」 「今更わかったか」 雨は少しずつ止み始めた。そして若島津の車はマンションの地下駐車場へと吸い込まれていく。 一日早いけれど、今夜も美味い酒を飲みながら夜を明かせそうだ。 若島津は車のキーを回してエンジンを止めた。 END
|